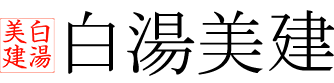みなさまは飲んでいる水が、金属のような味に感じることや、飲んだ印象が軽い、重いなどと感じることはありますか。実は、水にはさまざまなミネラルが含まれていて、ミネラルの種類や量の違いが、飲みやすさ、料理の適正、そして、極端な場合には健康に影響するほど水の性質を変えます。
この記事では、水のミネラル濃度の指標として使われる硬度について、そして水に含まれるカルシウムとマグネシウムの性質などについて紹介をしたいと思います。
水のミネラル量を表す硬度
水にはさまざまなミネラルが含まれていますが、中でも、カルシウム、マグネシウムは量が多く、飲用水の品質に与える影響が大きいです。このカルシウムとマグネシウムの濃度を合わせたものを、硬度と言い、ミネラル濃度の指標として広く使われています [1]。
また、硬度が高い水を硬水、低い水を軟水と呼びます。硬水は重たく飲みにくいのに対し、軟水はすっきりと飲みやすいため、水道水や市販のボトルウォーターの多くが軟水です。
硬水、軟水は一般的には、
硬水:硬度120 mg/L以上
軟水:硬度120 mg/L未満
と分類することが多いですが、厚生労働省の基準では、さらに細かく分類をしていて、
超硬水:硬度180 mg/L以上
硬水 :硬度120~180 mg/L
中硬水:硬度60~120 mg/L
軟水 :硬度60 mg/L未満
とされています [1]。中硬水という言葉はあまり使われることがありませんが、超硬水という言葉は一般の方でも、ご存じかもしれません。
水のミネラル濃度が変わる理由
水源の違いが硬度に与える影響
では、どうしてこのように水に含まれるミネラルの量が変わるのでしょうか?その違いは水源と土壌との関係から来ています。
水に含まれるミネラルは土壌のミネラルが抽出されたものです。そのため、なだらかな河川では土壌に触れる時間が長いため、ミネラルがたくさん抽出され、急な河川では抽出されにくいです。また、同じ理屈で、河川の上流では、ミネラルが少なく、下流に行くほどミネラルが蓄積され、多くなります。
国内の水の硬度を調べた研究では、関東地方が比較的硬度が高く、その理由として利根川の下流域に上水道設備があるからと述べられています [2]。一方で東北地方などの硬度は低く、この理由として、雪解け水が土壌と触れないためと述べられていました。
また、水源が地下水の場合には、土壌からミネラルがたくさん抽出されていくため、一般的には河川よりも硬度が高いです。
このように水源の環境によってミネラルの量が変わるというのはとても興味深いですね。
土壌の違いが硬度に与える影響
ここまで水源の違いが硬度に与える影響を紹介しましたが、次に土壌の違いが硬度に与える影響についても紹介したいと思います。
土壌は大まかに石灰岩の地域と花こう岩の地域に分かれますが、石灰岩には水に溶けやすい炭酸カルシウムが多く含まれていることから、硬水になりやすいです。
日本の土壌は花こう岩の土壌が広がっていることに加え、山地が多く、河川も急なことから軟水になりやすい条件が重なっています。一方で、ヨーロッパは地下水が多い上に、石灰岩の地域が多いため硬水が多いです。
ミネラルの違いを生活に生かそう
硬度の違いを料理に生かす
つぎに、硬度の違いが私たちの生活にどのように影響するかを、具体的に紹介したいと思います。
初めに料理ですが、一般的にミネラルは栄養成分と結合する性質があり、この性質を上手に使うことができれば雑味を取り除けますし、悪い方向に働くと栄養成分やうまみを失ってしまいます。
例えば軟水が好まれる例としては、昆布やかつおだしなどのようにうまみ成分を抽出したい場合、煮込み料理で野菜にしっかりと味をしみ込ませたい時などに向いています。
一方で硬水が好まれる例としては、肉をやわらかく煮込みたいとき、野菜の煮くずれを防ぎたいときなどに向いているようです [3]。ただし、肉を煮込む試験では、硬水の中でも硬度300程度のものが最も柔らかくなり、硬度が1000をこえる水で煮込んだ時は逆に硬くなったようです。
その他に、コーヒーでは、雑味を取り除き、すっきりとした味になるため、深煎りやエスプレッソコーヒーでは硬水が好まれますが、もともと、雑味が少なく、すっきりとした味になる水出しコーヒーなどでは軟水が好まれます。
このように、水の硬度まで気にして料理ができると素晴らしいですね。
硬度の違いが健康に影響する
次に、水の硬度がどのように健康に影響するかを紹介したいと思います。
硬水は、何と言ってもミネラルが多いことが魅力です。ミネラルの摂取による健康効果を直接体感することは難しいとは思いますが、カルシウムは骨を丈夫にしますし、マグネシウムには便秘を改善する機能があります [4]。さらに、これらの栄養成分の不足が生活習慣病の発症原因になるとも言われています [4]。
一方で軟水はミネラルが少ない分、体への負担も少ないため子供から大人まで安心して飲むことができるのが魅力です。
さいごに
この記事をまとめると、水には硬水と軟水があること、そして、このような硬度の違いが土壌や水源の違いからくることなどを紹介し、最後には硬水と軟水の長所を比較しました。
ミネラルが水から摂取できると考えると硬水は魅力的ですが、そうは言っても、すっきりと美味しく飲める軟水も捨てがたいですね。また、料理の際の長所を知っていると料理の楽しみが増えるのではないでしょうか。
興味がわいた方は、ヨーロッパのボトルウォーターは硬水が多いので、一度比較してみてください。
- 厚生労働省 カルシウム・マグネシウム等(硬度)
- Hori M, Shozugawa K, Sugimori K, Watanabe Y. A survey of monitoring tap water hardness in Japan and its distribution patterns. Sci Rep. 2021;11(1):13546. Published 2021 Jun 29. doi:10.1038/s41598-021-92949-8
- 鈴野弘子, 石田裕, 水の硬度が牛肉,鶏肉およびじゃがいもの水煮に及ぼす影響, 日本調理科学会 2013; 46(3):161-169. doi:10.11402/cookeryscience.46.161
- 厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)